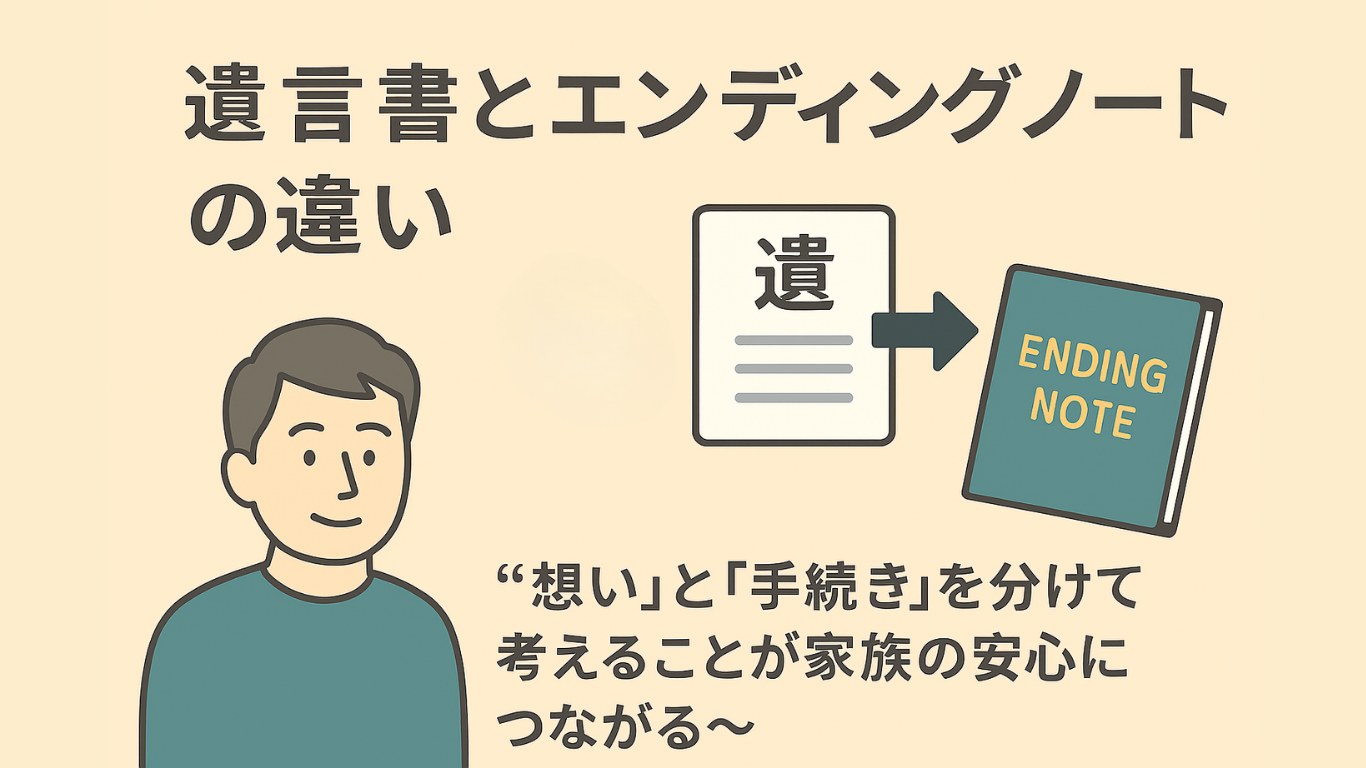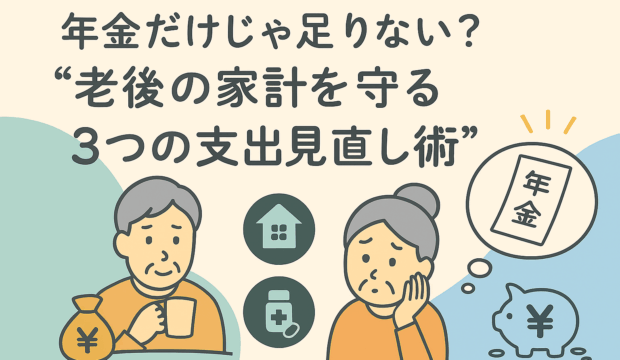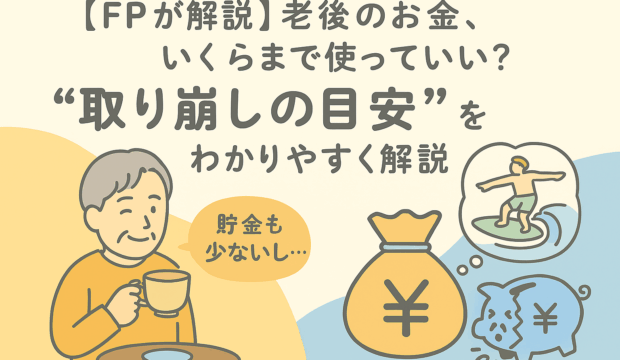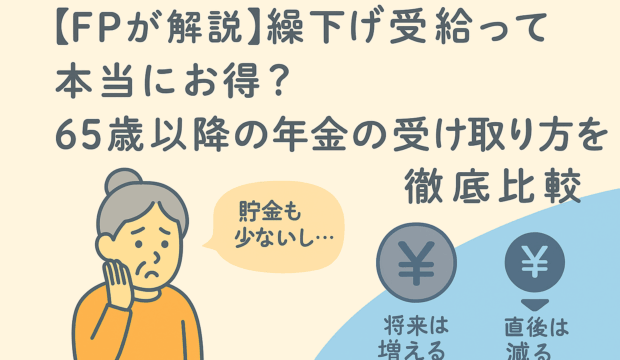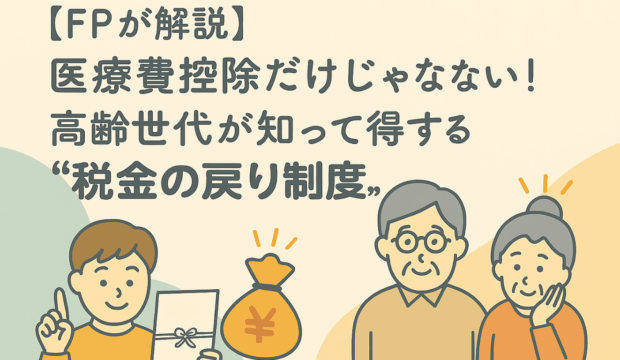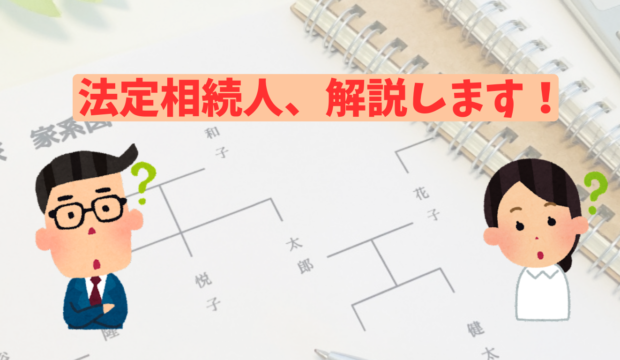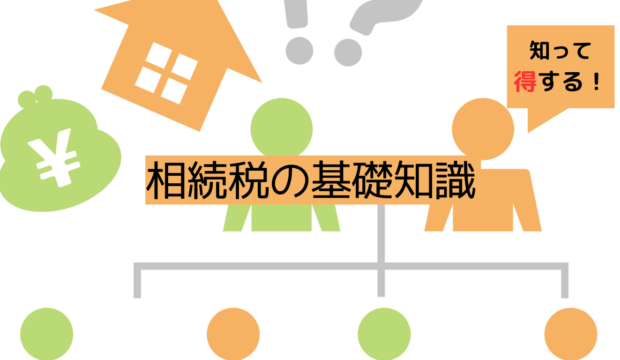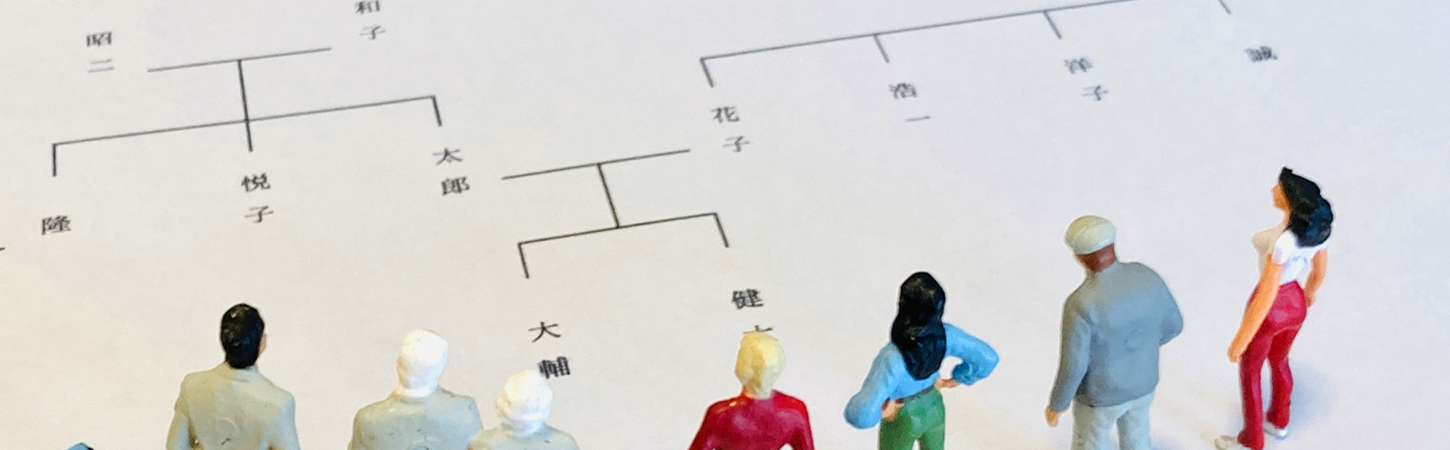「遺言書って難しそう」「エンディングノートがあれば十分?」
そんな声をよく耳にします。
実はこの2つ、目的も法的な効果もまったく違うもの。
どちらも大切ですが、「何を残したいのか」を明確にすることで使い方が変わります。
相続を“争い”にしないためには、法的に有効な手続きと、心を伝える記録の両方が必要です。
今回は、FPとしての視点から、それぞれの特徴と上手な使い分けを分かりやすく紹介します。

遺言書=「法的に効力を持つ指示書」
遺言書は、法律上の効力を持つ正式な文書です。
財産の分け方や、誰に何を相続させるかなどを明確に記します。
代表的な種類は3つ。
・自筆証書遺言:自分で全文を書く方法。手軽だが形式に注意。
・公正証書遺言:公証人が作成。費用はかかるが確実。
・秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証役場で保管。
土地や建物は分けにくいため、換価分割(売却して分ける)や代償分割(現金で調整)など、現実的な方法を検討しておきましょう。
| 種類 | 作成方法 | 保管場所 | 費用 | メリット | 注意点・デメリット |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 自筆証書遺言 | 遺言者が全文・日付・署名を自分で手書き(2020年以降は財産目録のみパソコン作成も可) | 自宅または法務局で保管可能(法務局保管制度あり) | ほぼ無料(印紙代など少額) | 手軽・すぐ作れる・費用がかからない | 書式不備で無効になるリスク。発見されない・隠される恐れもある |
| ② 公正証書遺言 | 公証人が本人の口述をもとに作成。証人2名が立ち会う | 公証役場で原本を保管 | 数万円程度(財産額による) | 確実・家庭裁判所の検認不要・紛失の心配なし | 証人が必要・費用がかかる・内容を完全に秘密にはできない |
| ③ 秘密証書遺言 | 本人が署名・押印した遺言書を封印し、公証役場で「確かに存在する」と証明してもらう | 本人または家族が保管 | 公証人手数料あり | 内容を秘密にできる・自筆であることが証明される | 内容確認ができないまま保管される・形式不備で無効の可能性が高い |
エンディングノート=「想いを伝える記録ノート」
一方、エンディングノートには法的な効力はありません。
しかし、家族の立場から見ると、これは非常に価値のある“心のガイドブック”です。
たとえば、
・医療や介護の希望
・お葬式の形式やお墓のこと
・親しい人への感謝のメッセージ
・各種IDやパスワードの保管場所
法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、遺言書とエンディングノートを一緒に管理することも可能です。

両方をそろえて“争わない相続”へ
理想は、遺言書で手続き、エンディングノートで想いを伝えること。
法的な部分だけ整えても、感情のすれ違いで揉めることがあります。
「想い」と「手続き」の両輪があることで、真の安心が生まれます。
・遺言書の内容を“数字”で整理し
・エンディングノートで“気持ち”を言葉にする
この2つを同時に整えることが大事です。
難しければ専門家のサポートを受けることも選択肢に入れておきましょう。
まとめ
遺言書とエンディングノートは、「どちらか」ではなく「どちらも」。
元気なうちに準備を始めておくことが、何よりも家族への思いやりです。
「何から手をつけたらいいかわからない」
そんなときは、ぜひご相談ください。
“想い”と“手続き”の両面からサポートする相続準備をお手伝いします。