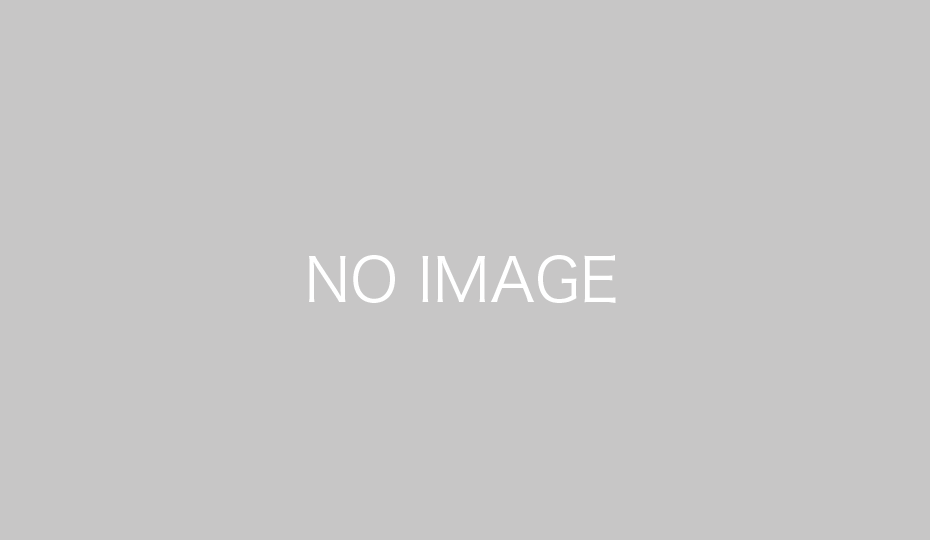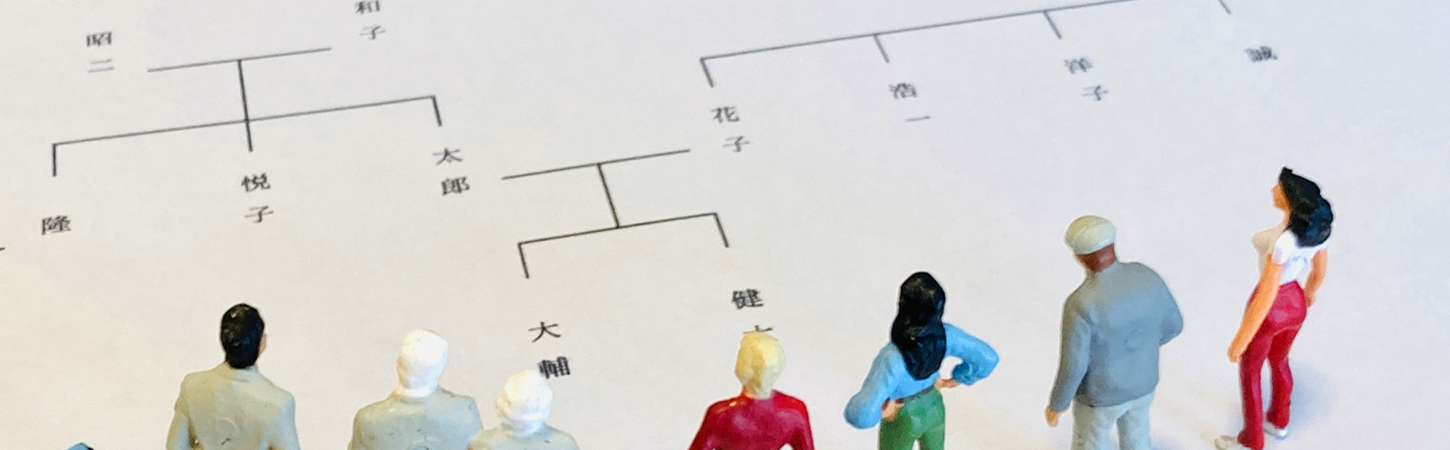「手術で入院したら医療費が思ったより高くて驚いた…」
そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
健康保険があるから安心と思っていても、3割負担であっても数十万円単位の請求になることがあります。
しかし、「高額療養費制度」を知っていれば、その負担をぐっと抑えることができます。
今回はFPとして、制度の仕組みや申請の流れ、そして実際にどのくらい軽減できるのかを具体的に解説します。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、1か月(1日〜末日)に支払った医療費が、所得に応じた上限額を超えた場合、超過分が払い戻される仕組みです。
この制度は健康保険・国民健康保険いずれにも共通しており、入院・外来・手術などが対象になります。
たとえば、手術や長期入院で医療費が100万円かかった場合、3割負担の自己負担額は30万円。
しかし高額療養費制度を使うと、年収約500万円の世帯なら月の自己負担は約8万7,000円までに抑えられます。
差額ベッド代や食事代は対象外ですが、それでも20万円以上が戻ってくるケースもあります。
自己負担限度額の目安と計算式
限度額は「年齢」と「所得」で異なります。69歳以下の場合、次のように計算されます。
| 区分 | 目安年収 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|---|
| 区分ア | 約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
| 区分イ | 約770万〜1,160万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
| 区分ウ | 約370万〜770万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 区分エ | 約370万円以下 | 57,600円 |
| 区分オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
つまり、年収500万円の人が医療費50万円を支払った場合、自己負担は「80,100円+(500,000−267,000)×1%=約82,400円」となります。
これを超えた分(約67,600円)は、後日払い戻しされます。
FPの視点
同一世帯で複数人が同月に医療費を支払っている場合、「世帯合算」も可能。
家族全員の医療費を合算して上限を超えた分も戻るため、共働き世帯や高齢夫婦にも大きなメリットがあります。
申請方法とタイミング
高額療養費制度の申請には「限度額適用認定証」などを保険者へ申請する方法が一般的ですが、最近ではマイナ保険証の活用によって、手続きの簡素化が進んでいます。
▶ 事前手続き:「限度額適用認定証」と「マイナ保険証」の違い
・限度額適用認定証:
入院・手術が予見できる場合に保険者へ申請し、認定証を受けて医療機関窓口で提示します。これにより、支払い時点で自己負担限度額までになるため、後日払い戻しを待つ必要が少なくなります。
・マイナ保険証を活用する方法:
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録し、受診時に 医療機関が“オンライン資格確認”で限度額情報を取得できる環境 であれば、 限度額適用認定証の事前申請が不要 です。
つまり、窓口で支払う金額があらかじめ自己負担限度額までに調整されるケースがあります。
ただし、医療機関がオンライン資格確認対応していない場合や、低所得者(住民税非課税世帯など)の方については、これまで通り申請が必要なケースがあります。
▶ 事後手続き:支払後の申請(申請書提出)
もし認定証の提示やマイナ保険証の利用ができなかった場合でも、窓口支払い後に保険者へ「高額療養費支給申請書」を提出すれば、対象額が医療費から自己負担限度額を超えた分として返還されます。申請期限は 支払った月の翌日から2年以内 が基本です。
FPの視点
マイナ保険証を持っていても、受診する医療機関がマイナ保険証に対応できるところでないと意味がありませんので、事前に確認しておくことがおすすめです。
知っておきたい「多数該当」と「世帯合算」
高額療養費制度には、さらに負担を軽くする仕組みもあります。
・多数該当制度:
過去12か月以内に3回以上、高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは上限額がぐっと下がります。
たとえば、年収500万円の人なら、4回目以降の上限は約4万4,400円に。
慢性疾患や通院治療が続く方には大きな助けになります。
・世帯合算制度:
同一世帯で複数人が医療機関を利用した場合、合計で上限を超えた分が支給対象に。
たとえば、夫が入院・妻が通院で、それぞれの支払いが小さくても、合算すれば上限を超えるケースがあります。
制度をどう活かすか
高額療養費制度はとてもありがたい制度ですが、実際には「知らなくて申請していなかった」「限度額認定証を出し忘れた」という方が多いのも現実です。
また、差額ベッド代・食事代・交通費・先進医療費は対象外なので、全額が戻るわけではありません。
そのため、FPとしては次の3つの備えをおすすめします。
1️⃣ 民間の医療保険で自己負担をカバー
例:入院1日5,000円の給付があれば、差額ベッド代や食費分に充当可能。
2️⃣ 生活防衛資金を準備
払い戻しまで数か月かかるため、一時的な立替資金を確保しておくこと。
3️⃣ 介護・老後資金と分けて管理
医療費・介護費・生活費を一緒に管理すると見えづらくなります。
「医療費口座」をつくっておくのも一案です。
まとめ
高額療養費制度は、誰にでも利用できる公的な「医療費の安全網」です。
ただし、所得や年齢によって上限額が違い、申請しなければ払い戻されない点には注意が必要です。
「いざというときに慌てないために、今のうちに“認定証を申請しておく”」
そして「医療費がどの程度かかっても家計が耐えられる仕組み」を考えることが、安心な生活の第一歩です。
『うちの場合はいくらまで補助が出る?』『どんな備えをしておくと安心?』と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
制度のしくみだけでなく一緒に「実際の家計数字」で整理し、無理なく安心できるプランを作成します。