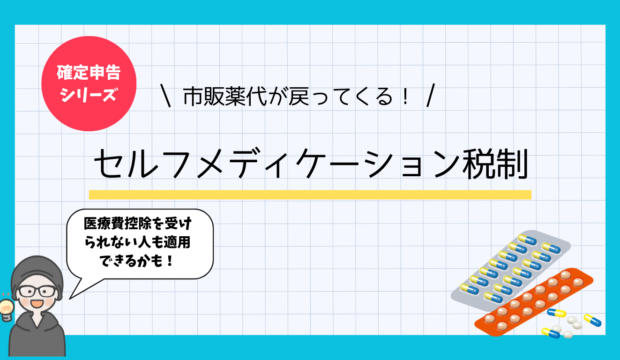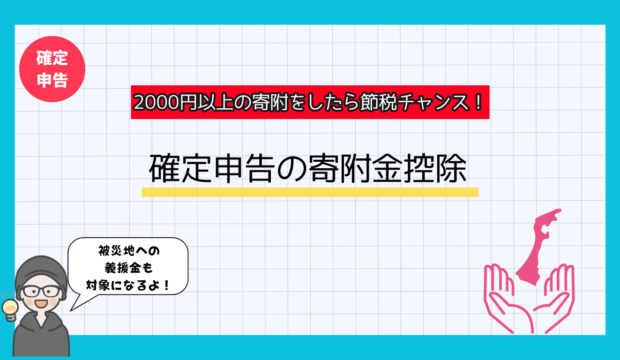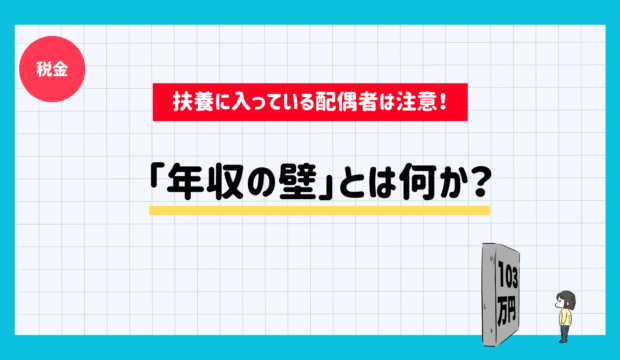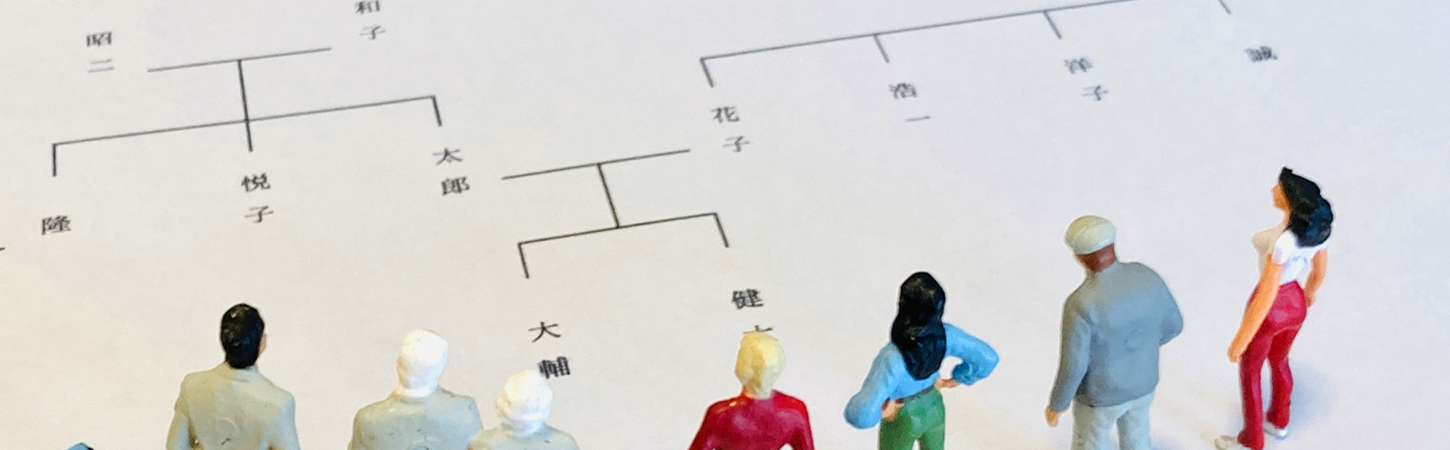年末が近づくと、会社から「保険料控除証明書を提出してください」「扶養控除の申告書を出してください」といった案内が届きます。
毎年のことですが、共働き家庭にとってこの作業はちょっと厄介ですよね。
「子どもの扶養はどちらがつけるの?」
「生命保険の控除証明書、どっちが申告すればいい?」
「医療費って合算してもいいの?」このような疑問をそのままにしておくと、気づかないうちに数万円単位の税金を払いすぎているケースもあります。
今回は、共働き家庭が年末調整で損をしやすい4つのポイントを、FP視点でわかりやすく解説します。
①:生命保険料控除 ― 契約者と支払者が一致しているか?
生命保険料控除は、誰が契約して、誰が保険料を払っているかが重要です。
「妻の口座から引き落とされているけど、契約者は夫」など、よくあるケースでは、控除を受けられるのは契約者の夫です。
もし夫婦どちらも控除を受けたい場合は、契約を分ける・名義を見直すなど、翌年以降の準備が必要です。
また、旧制度・新制度の控除額の違い(最大12,000円~40,000円)も見逃しがちなので、証明書に記載の「新旧区分」も確認しておきましょう
POINT・契約者と支払者が同じか確認
・旧制度・新制度のどちらかをチェック
・必要なら翌年以降に契約を見直す
②:扶養控除 ― 所得の高い方がつけたほうが有利な場合が多い
共働き家庭でよくあるのが、「子どもをどちらの扶養に入れるか」という問題。
扶養控除は、所得税率の高い方が受けたほうが節税効果が大きくなります。
たとえば、夫の年収600万円・妻の年収400万円の家庭で子ども1人を扶養に入れた場合、夫側で申告したほうが所得税率が高いため、控除による節税額が増えます。
ただし注意したいのは、児童手当や保育料の算定。
これらは「世帯主」ではなく「所得の高い方の収入」で判断されるため、税金面だけでなくトータルの家計メリットを見て決めるのが大切です。
POINT・所得が高い方が扶養をつける
・児童手当・保育料の影響も考慮
・共働きでも二重申告はNG(重複すると修正申告になる)
③:医療費控除 ― “世帯合算OK”でも申告者の選び方にコツあり
1年間に支払った医療費が10万円を超えたら、医療費控除のチャンスです。
共働きでも、同一生計であれば夫婦・子どもの分を合算できます。
ただし、誰の名義で確定申告するかによって節税効果が変わります。
たとえば、所得が低い妻が申告したほうが「控除の割合が高くなる」こともあります。
POINT・世帯全体の医療費を合算してよい
・確定申告でのみ申請可能(年末調整では不可)
・所得の低い方が有利になるケースも
医療費通知(健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」)や領収書の整理は、12月中に済ませておくと確定申告がスムーズです。
④:住宅ローン控除 ― 夫婦共有名義は“持分割合”を確認
マイホームを購入した共働き家庭では、「住宅ローン控除」を忘れずに。
夫婦それぞれが住宅ローンを組んでいれば、それぞれが控除を受けることができます。
ただし注意が必要なのは、登記上の持分割合と実際の返済割合が一致していないケース。
たとえば、登記では夫50%・妻50%でも、返済はほぼ夫が行っている場合、税務署で問題になることがあります。
POINT・1年目は確定申告が必要
・持分と返済割合が一致しているか確認
・2年目以降は勤務先で年末調整OK
まとめ:夫婦で“税金の分担”を話し合うことが最大の節税
共働き家庭では、「お互いの収入」「控除対象の名義」「支払口座」などが別々になりやすく、知らないうちに控除を取りこぼしているケースが多いです。
実際に、FP相談の現場でも「保険料控除をどちらも出していた」「医療費控除を夫婦でバラバラに出した」など、修正申告につながる事例が後を絶ちません。
年末調整のタイミングは、夫婦で一度お金の流れを整理する絶好の機会です。
もし迷ったら、控除証明書を並べて“誰が出すか”を話し合うだけでも効果的です。
たった30分の見直しで、数万円の節税につながるかもしれません。