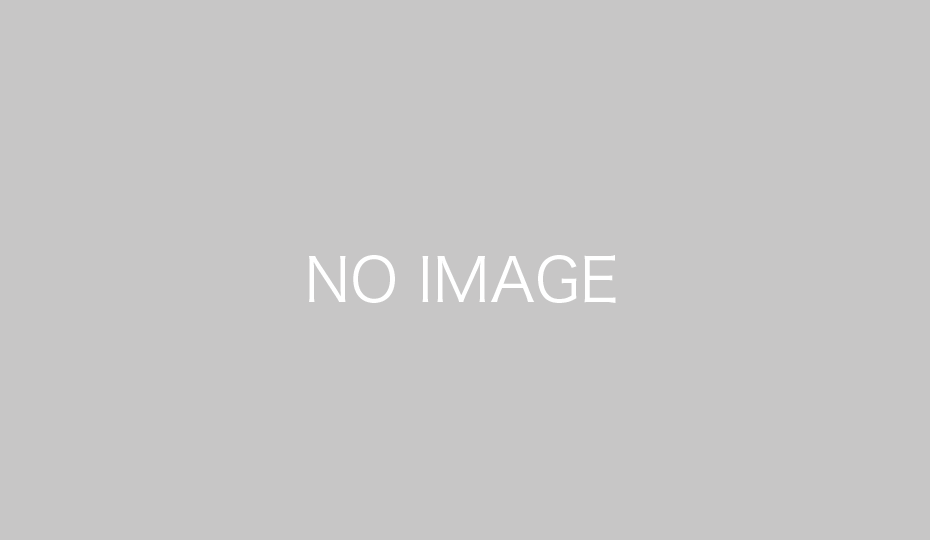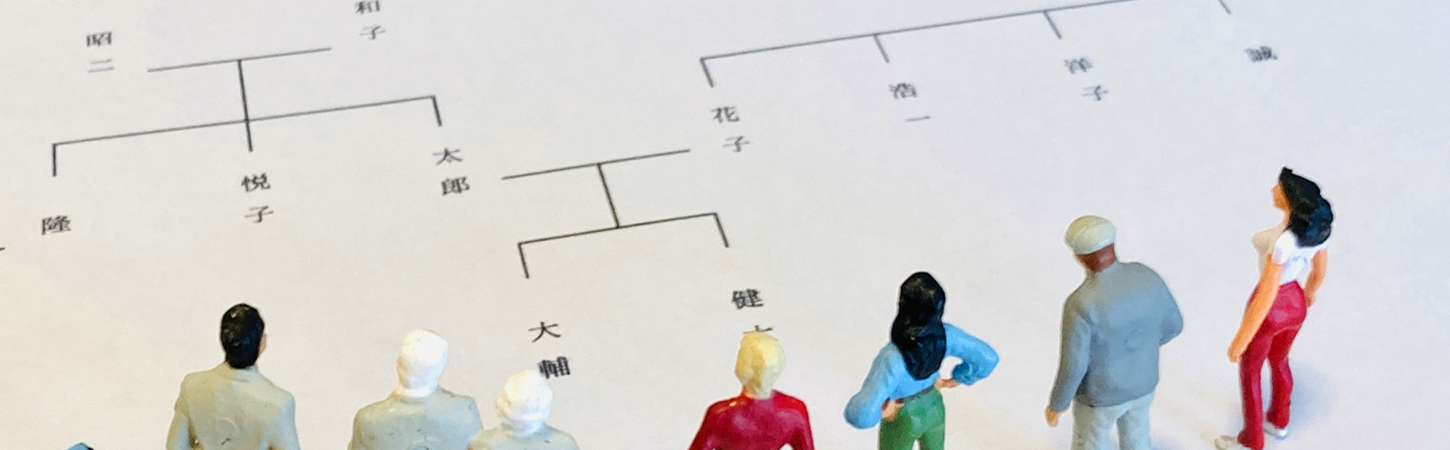毎年届く「固定資産税の納税通知書」。
中身を見て「去年より高い?」「うちの土地ってそんなに価値あるの?」と感じたことはありませんか?
実はその背景には、“土地の評価額”が実際の状況と合っていないことがよくあります。
特に、地価が下がっている地域や、使っていない土地を持っている人は、見直しによって税金を減らせる可能性があります。
今回は、不動産とお金の専門家の視点から、土地評価額の仕組みと見直しの方法をわかりやすく解説します。
そもそも「固定資産税」はどうやって決まる?
固定資産税は、市町村が毎年1月1日時点の土地や建物の「評価額」に基づいて計算します。
計算式はとてもシンプルです。
固定資産税額 = 評価額 × 1.4%(標準税率)
この「評価額」は、3年に一度見直される仕組みで、国が定める「固定資産評価基準」に沿って市町村が算出します。
一般的に、実際の取引価格(時価)の約7割が目安とされています。
ところが、地価が下がっているのに評価額がそのまま据え置かれていたり、土地の形状や利用状況が十分に考慮されていなかったりすることが多く、“実態より高い評価”になっているケースもあります。
都市計画税も一緒に課税されることに注意!
固定資産税と並んで、見落とされがちなのが「都市計画税」です。
これは、市街化区域内にある土地や建物に対して課される税金で、都市のインフラ整備(道路・下水道など)に使われる目的税です。
計算式は以下の通りです。
都市計画税 = 評価額 × 0.3%(上限)
つまり、評価額が高すぎると「固定資産税」だけでなく「都市計画税」も同時に高くなります。
逆に言えば、評価額の見直しによって両方の税負担を軽減できる可能性があるということです。
特に伊東市のように、市街化区域と調整区域が混在する地域では、土地の位置によって都市計画税の有無が分かれます。
自分の土地がどちらに該当するか、課税明細書で確認しておきましょう。
評価額が高すぎる土地の特徴
次のような場合は、見直しの余地があるかもしれません。
✅地価が下がっている地域なのに評価額が変わっていない
✅傾斜地や崖地など、使いにくい地形なのに通常評価されている
✅私道にしか面していないのに、一般道路扱いになっている
✅細長い旗竿地なのに、普通の宅地と同じ評価
✅空き地・遊休地が宅地並みに課税されている
こうした土地は、市区町村に「評価額の見直し」を求めることで、税額の軽減につながる可能性があります。
評価額を見直す手順
-
課税明細書をチェック
まず、毎年届く「固定資産税・都市計画税課税明細書」を確認しましょう。
土地の面積、地目、評価単価などが記載されています。
不明点があれば、市役所の資産税課で説明を受けられます。 -
路線価・公示価格と比較する
国税庁の「路線価図」や国土交通省の「地価公示」サイトで、 自分の土地の周辺価格を確認できます。
もし評価額が周辺より明らかに高ければ、見直しのチャンスです。 -
近隣の土地と比較する
同じエリアで似た条件の土地がどの程度の評価か調べることで、 バランスの取れた判断ができます。 -
専門家に相談する
不動産会社やFPに相談すれば、 「適正評価なのか」「見直しすべきか」を客観的に見てもらえます。
特に、相続で引き継いだ土地や空き地などは相談価値が高いです。 -
市町村に「審査申出」を行う
評価に不服がある場合は、 「固定資産評価審査委員会」への申出が可能です。
通常、評価替え年度の翌年1月31日までが期限。
提出後、調査や現地確認を経て判断されます。
知っておきたい“減額特例”もある
見直しのほかにも、減額される特例制度を利用できる場合があります。
・住宅用地の特例:200㎡以下なら評価額の1/6に軽減
・災害による損壊地の減免:地震・台風などで被害が出た場合
・空き家の特例:倒壊の恐れがある空き家を撤去した場合に軽減
これらを組み合わせると、実質的に数万円〜数十万円の節税効果が期待できます。
まとめ:放置せず“見直す”ことで資産を守ろう
固定資産税と都市計画税は、毎年自動的に請求されるため、つい「仕方ない」と思いがちです。
しかし、土地の評価額を定期的にチェックし、実態に合っていない場合は見直すことで、無駄な税負担を減らすことができます。
特に相続で引き継いだ土地や、長年使っていない空き地は要注意。
そのままにしておくと、税負担だけでなく、管理費用や相続時の評価にも影響します。
「うちの土地、評価が高すぎるかも?」と感じたら、一度専門家に相談してみましょう。
正しい評価を知ることが、資産を守る第一歩になります。