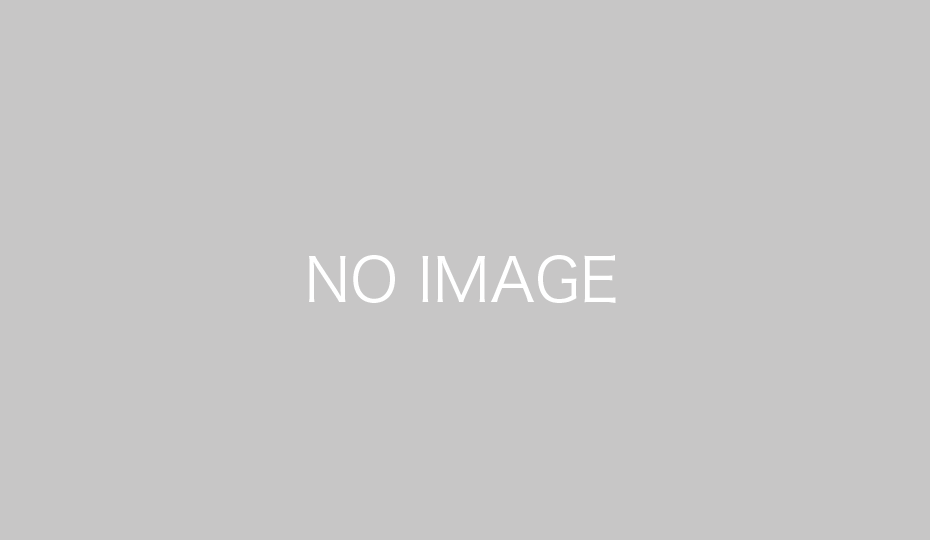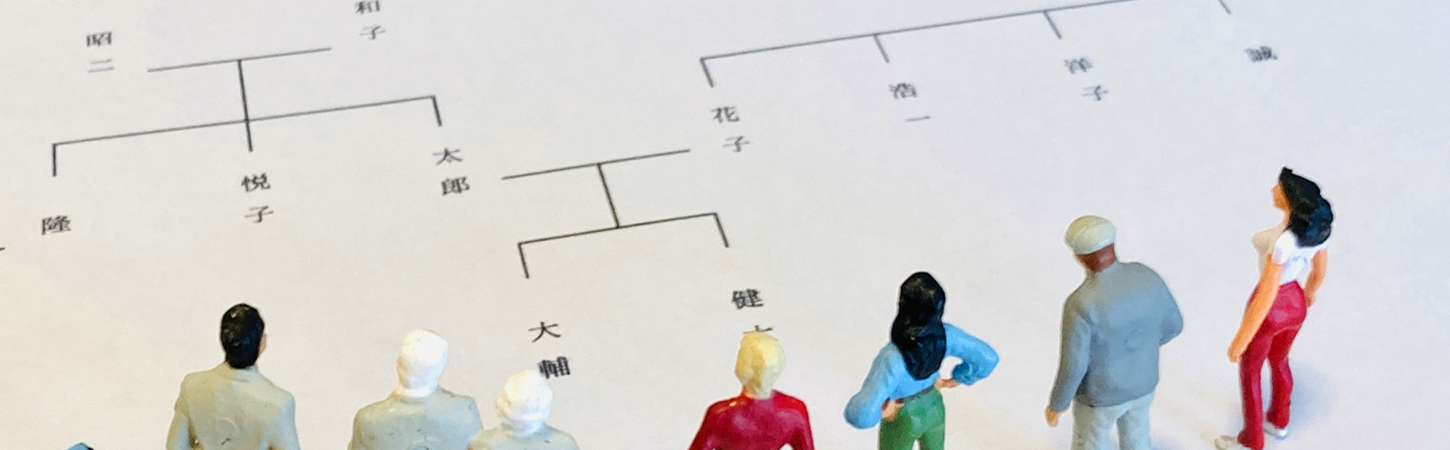「もし仕事を辞めたら…」に備える“雇用保険”の安心制度
働く人なら誰もが加入している「雇用保険」。
その中でも“失業給付”は、仕事を失ったときに次の職を探す間の生活を支える制度です。
ただし、申請のタイミングや離職理由によって給付額・支給開始日が変わるため、仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

失業給付とは?基本の仕組みをやさしく解説
雇用保険の失業給付(正式には「基本手当」)は、離職した人が「すぐに働く意思と能力を持っている」場合に、一定期間・一定額の給付を受けられる制度です。
支給額の目安
・給付額=離職前6か月の賃金日額 × 給付率(45〜80%)
・給付率は年齢や収入によって変わり、低所得者ほど高い率が適用されます。
支給日数
・離職理由・年齢・被保険者期間によって異なり、 最短90日〜最長330日まで。
・「自己都合退職」より「会社都合退職(倒産・解雇など)」の方が支給期間が長く設定されています。
手続きと支給までの流れ
1️⃣ 会社から離職票を受け取る
2️⃣ ハローワークで求職申込みを行う
3️⃣ 7日間の「待期期間」を経て、
4️⃣ 給付制限期間(自己都合退職の場合)終了後、支給が開始
この流れの中で、離職理由の確認が非常に重要です。
「自己都合」か「会社都合」かで給付日数や支給時期が大きく変わります。
特に、実際には会社都合に近いケースでも“自己都合扱い”になってしまうことがあるため、離職票の内容は必ず確認しましょう。
2025年の制度改正ポイント
失業給付制度は、より柔軟に働く人を支援する方向で改正が進んでいます。
自己都合退職者の給付制限が短縮
これまで自己都合退職の場合、2ヶ月間の給付制限がありましたが、2025年4月からは原則1ヶ月に短縮されます。
これにより、再就職活動を早く始めたい人がより利用しやすくなります。
教育訓練中の人への配慮が拡大
職業訓練や資格取得のための離職については、給付制限がかからない仕組みが整備されました。
FPとしても、「スキルアップを目的とした再出発」を後押しする制度として注目したいポイントです。
給付額の見直し(2025年8月〜)
賃金水準の変化を反映させるため、基本手当日額の上限・下限が見直されます。
これにより、賃金の高い層・低い層ともに、より実情に近い給付額が設定される予定です。
失業給付の支給までのステップ
| ステップ | 内容 | 自己都合退職(給付制限あり) | 会社都合退職(給付制限なし) |
|---|---|---|---|
| ① 離職 | 会社を退職 | ✔ | ✔ |
| ② 離職票の受け取り | 会社から「離職票」を受け取る | ✔ | ✔ |
| ③ 求職申込み | ハローワークで離職票を提出し、求職申込み | ✔ | ✔ |
| ④ 受給資格決定 | 離職理由の判定、説明会の案内 | ✔ | ✔ |
| ⑤ 雇用保険説明会 | 制度の説明、必要書類の配布 | ✔ | ✔ |
| ⑥ 待機期間(7日間) | 給付なし。就労不可 | ✔ | ✔ |
| ⑦ 給付制限期間 | 自己都合退職の場合、さらに1〜2ヶ月の給付制限(原則は1ヵ月だが例外あり) | 約1〜2ヶ月 | なし |
| ⑧ 求職活動 | 認定対象期間ごとに求職活動実績が必要 | 初回は1回以上 | 初回は1回以上 |
| ⑨ 初回失業認定日 | ハローワークで失業認定申告書を提出 | ✔ | ✔ |
| ⑩ 給付開始 | 認定後、約1週間で口座に振込 | 約1.5〜2ヶ月後 | 約1ヶ月後 |
失業給付を上手に活用するためのFP視点アドバイス
・再就職までの期間を見越して家計をシミュレーションすることが大切。
→「給付金+貯金」で生活費を何ヶ月まかなえるかを確認しましょう。
・教育訓練給付金との併用もおすすめ。
資格取得を目指す場合は、一定条件で給付率が上がることもあります。
・離職前に「いつから給付が始まるか」を逆算しておくと、生活資金の準備に余裕が持てます。
制度改正で使いやすくなった一方、「申請のタイミング」「離職理由の分類」によって損をする人も少なくありません。
不安なときは、退職前にFPに相談し、「手続き・時期・受給額」をシミュレーションしておくと安心です。
まとめ──“知っているかどうか”で変わる安心度
失業給付は、単なるお金の支援ではなく、次のステップへの“助走期間”を支える制度です。
2025年の改正で、より早く・より柔軟に受け取れるようになりました。
「うちの場合、どのくらいもらえる?」「再就職までの資金は足りる?」
そんな疑問が浮かんだら、早めに制度を確認しておきましょう。