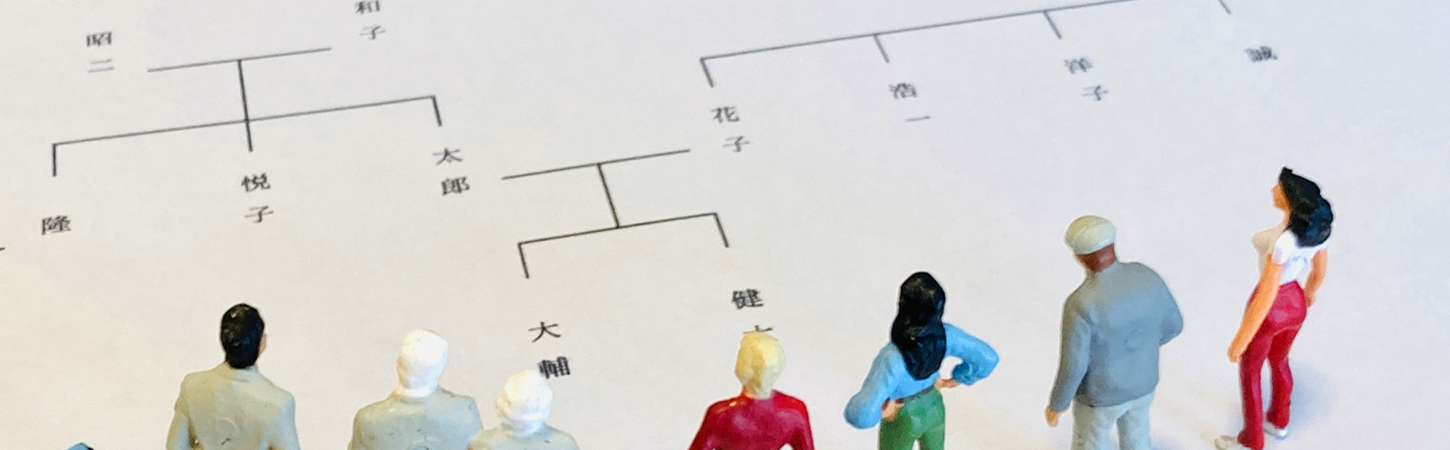物価高で生活費が上がる中、家計を支えてくれるのが「補助金」や「給付金」。
ところが、申請しなければもらえない制度がほとんどです。
せっかくの支援を見逃している家庭も多く、FP相談でも「そんな制度があるなんて知らなかった!」という声をよく聞きます。
今回は、子育て世帯が今すぐチェックすべき主要な補助金をまとめました。

定番の補助金・給付金をおさらい
まずは全国どこでも受けられる「基本の3制度」から確認しましょう。
| 制度名 | 対象 | 支給額(例) | ポイント |
|---|---|---|---|
| 児童手当 | 0歳〜高校生まで | 月1万円〜1.5万円 | 2024年10月から高校生まで対象拡大・所得制限撤廃 |
| 出産・子育て応援給付金 | 妊娠〜出産後1歳未満 | 合計10万円(出産時5万+育児期5万) | 妊婦面談などとセットで申請が必要 |
| 児童扶養手当 | ひとり親世帯 | 月最大4.3万円前後(所得に応じて変動) | 臨時給付金の上乗せ支給がある自治体も |
FPメモ
どれも申請しないと自動で受け取れません。
出産・転居・子どもの進学など「ライフイベントごと」に申請内容が変わるため、更新を忘れずに。
自治体独自の支援を見逃さない!
国の制度だけでなく、市区町村ごとに独自の支援制度があります。
たとえば、静岡県内でも以下のような違いが見られます。
・保育料・給食費補助:第2子以降が無料、あるいは半額。
・医療費助成:高校卒業まで医療費が実質無料の自治体も。
・高校生通学費補助:定期代・バス代の一部を補助。
・住宅関連補助:省エネ改修・リフォーム補助金で最大200万円支給されるケースも。
FPメモ
自治体のHPは「制度一覧」ページが分かりにくいこともあります。
「〇〇市 子育て支援 補助金」とGoogleで検索すると早く見つけられます。
これから始まる「子ども・子育て支援金制度」
26年度からスタート予定の新制度。
企業と個人が保険料のように拠出し、少子化対策の財源に充てる仕組みです。
この制度によって、「児童手当のさらなる拡充」や「保育料の軽減」などが期待されています。
FPメモ
今後は「現金給付+サービス支援」の二重構造になります。
制度開始までの間に、今ある支援を漏れなく活用しておくことが重要です。
申請漏れを防ぐために
✅ 自治体の公式サイトを月1回チェック
自治体ごとに支援制度が異なり、募集期間が短いものも多いです。
「気づいた時には受付が終わっていた…」というケースを防ぐためにも、定期的な確認が安心。
特に年度末(2〜3月)は新しい制度が発表されるタイミングです。
✅ ライフイベント(出産・進学・転居)ごとに再確認
制度の対象は、子どもの年齢や居住地の変化によって変わります。
転居や進学の際に「以前の自治体では対象だったのに、今の自治体では対象外」というケースも少なくありません。
イベントごとに“チェックリスト”をつくっておくと、もれなく申請できます。
✅ 確定申告の際に関連控除を見直す
確定申告の時期は、補助金と控除を一緒に整理する絶好のチャンスです。
扶養控除・医療費控除・寄附金控除などを見直すことで、申告漏れによる損失を防げます。
「税金の控除」と「給付金の申請」は別々に思われがちですが、実際には密接に関係しています。
FPの視点
制度は毎年少しずつ変わります。
ニュースやSNSの情報も参考になりますが、最終的には「自治体の公式情報」を基準に判断するのが安心です。
もし「調べるのが大変」「自分の家庭がどれに当てはまるかわからない」という場合は、FPに家計診断を依頼するのもおすすめです。
制度活用の有無で、年間にして数万円の違いが出ることも珍しくありません。
まとめ──補助金は「家計の第3の収入源」
「働いて得る」「投資で増やす」に加えて、「制度で受け取る」ことも立派な家計戦略です。
補助金・給付金は“もらえる人だけが得をする”世界。
FPとしては、「制度を知って申請すること」こそが最も確実な家計改善の第一歩だと考えます。
「うちはどれに該当する?」と思ったらお住まいの自治体ページを確認し、必要ならFPに相談してみましょう。
制度をうまく活用できれば、家計の安心感がぐっと変わります。