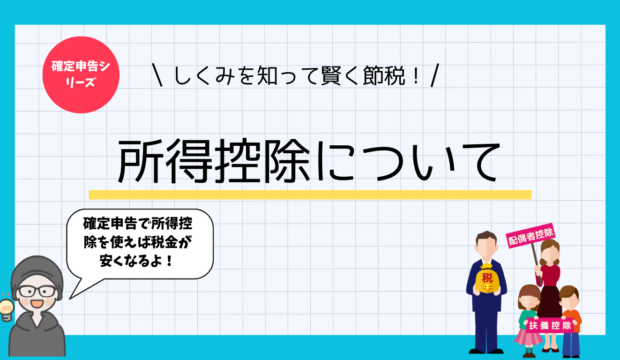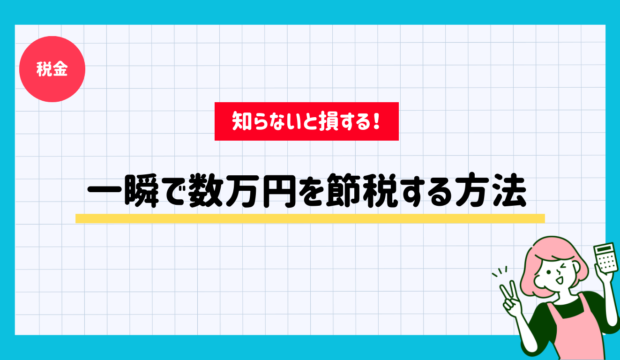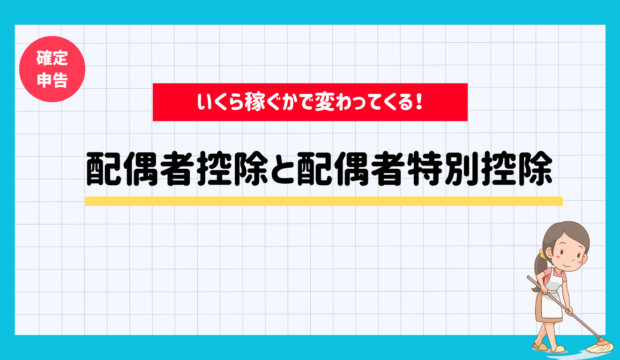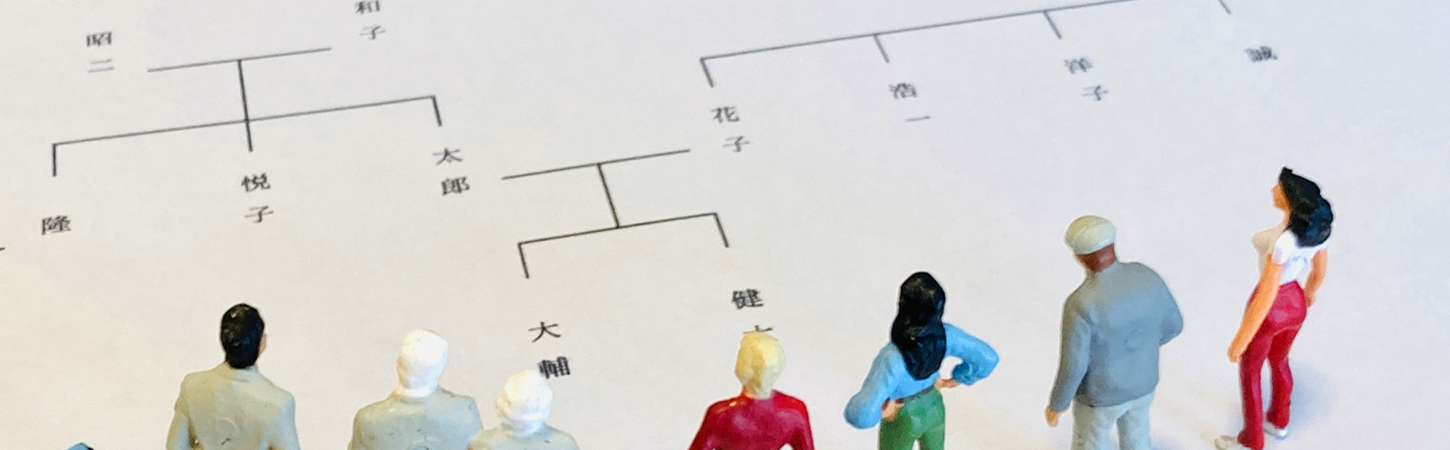「確定申告は自営業の人だけのもの」と思っていませんか?
実は会社員でも、自分で確定申告をすれば税金が戻ってくるケースがあります。
それは単なる節税ではなく、“お金を守り、育てる第一歩”です。
今回は、“サラリーマンが確定申告で得する7つの控除”をわかりやすく解説します。
年末調整と確定申告の違いをおさらい
・年末調整:会社が給与から天引きした税金を自動で精算する手続き。
・確定申告:自分で支出を申告し、払い過ぎた税金を取り戻す仕組み。
・会社が把握できない「医療費・寄附金・住宅購入」などは年末調整に含まれない。
| 区分 | 年末調整でできること | 年末調整でできないこと(=確定申告が必要) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 会社が給与から天引きされた税金を精算する | 個人が自分で支出や特別な所得を申告する |
| 手続きする人 | 勤務先(会社) | 本人(納税者) |
| 対象となる所得 | 給与所得のみ | 給与以外の所得(副業・不動産・株式など) |
| 控除できるもの | 生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除 | 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)・ふるさと納税(5自治体超)・寄附金控除(NPO等)・雑損控除・副業収入の申告など |
| 手続きの時期 | 毎年11月〜12月(勤務先指定) | 翌年2月16日〜3月15日 |
| 結果 | 還付・徴収は給与で自動調整 | 税務署またはe-Taxで還付・納付を行う |
| ポイント | 会社任せで簡単だが控除は限定的 | 申告することで“払い過ぎた税金”が戻ることも |
サラリーマンが申告しないと損する7つの控除
| 控除の種類 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 年間10万円超の医療費 | 家族分も合算OK、交通費も対象 |
| セルフメディケーション税制 | 指定薬品1.2万円超 | 医療費控除と選択制 |
| ふるさと納税 | ワンストップ特例を使わない場合 | 5自治体以上寄附なら申告必要 |
| 雑損控除 | 災害・盗難・詐欺被害 | 罹災証明書が必要 |
| 寄附金控除(NPO・学校など) | 公的寄附・認定法人等 | ワンストップ対象外 |
| 住宅ローン控除 | 初年度のみ確定申告必要 | 2年目以降は年末調整OK |
| 副業・雑所得控除 | 年間20万円超の収入 | 申告しないと住民税も過徴収 |
確定申告は“お金を育てる”行動でもある
「お金を増やす=資産運用」だけでなく、“税金や制度を正しく使うこと”もお金を育てる力の一つとされています。
無駄な税金を減らすこと=“守りの運用”
返ってきたお金をつみたてNISAなどに回せば、“攻めの運用”にもなる。
「お金を育てる=お金を流れさせる力」と考えれば、確定申告はその第一歩です。
2025年の確定申告で便利になったポイント
・マイナポータル連携で医療費・保険料・寄附金の情報が自動入力。
・マイナ保険証の利用履歴から医療費控除が自動反映。
・スマホe-Tax申告で自宅から申告完了。
💡 「確定申告=難しい」という時代は終わりつつあります。
FPが見る「確定申告をした方がいい人」
✅ 医療費が10万円超えた人
✅ 複数自治体にふるさと納税した人
✅ 家を購入・ローンを組んだ人
✅ 副業・ネット収入がある人
✅ iDeCo・NISAを始めた人(税金面も確認)
これらの項目に一つでも当てはまる人は、「確定申告でお金が戻る可能性がある人」です。
特に医療費やふるさと納税、住宅ローン控除の初年度などは、会社が自動で処理してくれない部分です。
“確定申告=手間がかかる”と思われがちですが、今はマイナポータルやe-Taxの活用でかなり簡単になっています。
たとえば、申告によって3万円~5万円の還付を受ける人も珍しくありません。
これは、「お金を増やす」よりも確実で安全な“お金を守る行動”です。
FPとしては、節約や投資よりも先に、まず税制度を正しく使うことをおすすめしています。
まとめ
確定申告は、“お金を増やす前に、まず守る”ための大切な仕組みです。
「お金を育てる」ためには、まず制度を正しく使いこなすこと。
税金をムダにせず、賢く取り戻すことが、豊かな未来を作る第一歩です。
「うちの場合どの控除が使える?」「申告のやり方が不安」という方はご相談ください。
手取りを増やす“確定申告プラン”をわかりやすくご案内します。