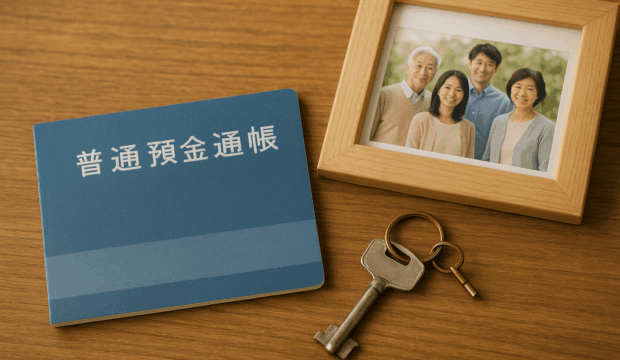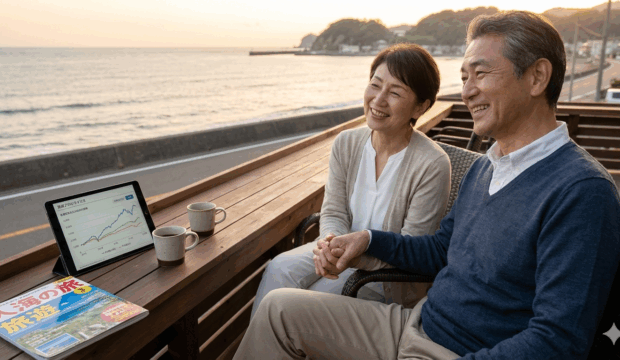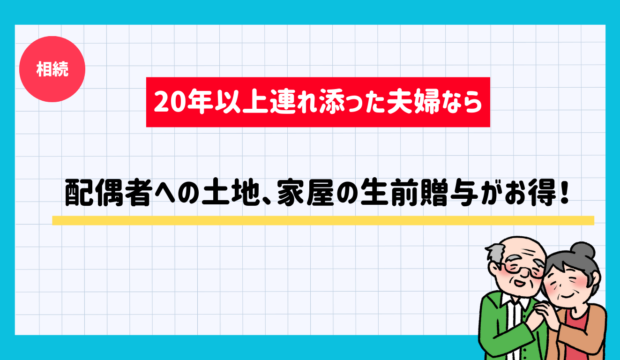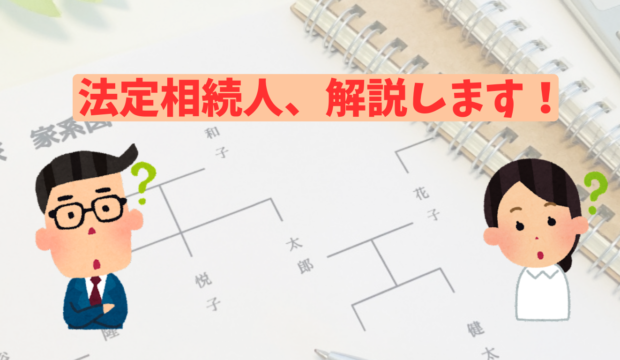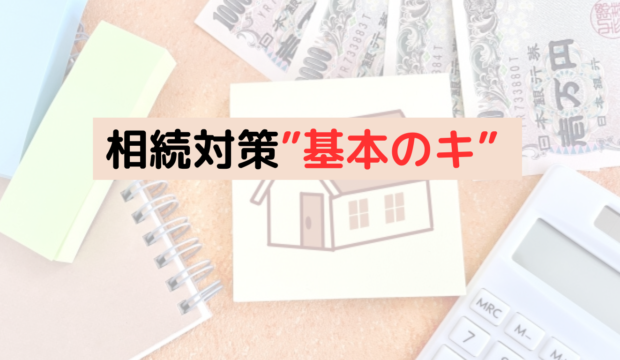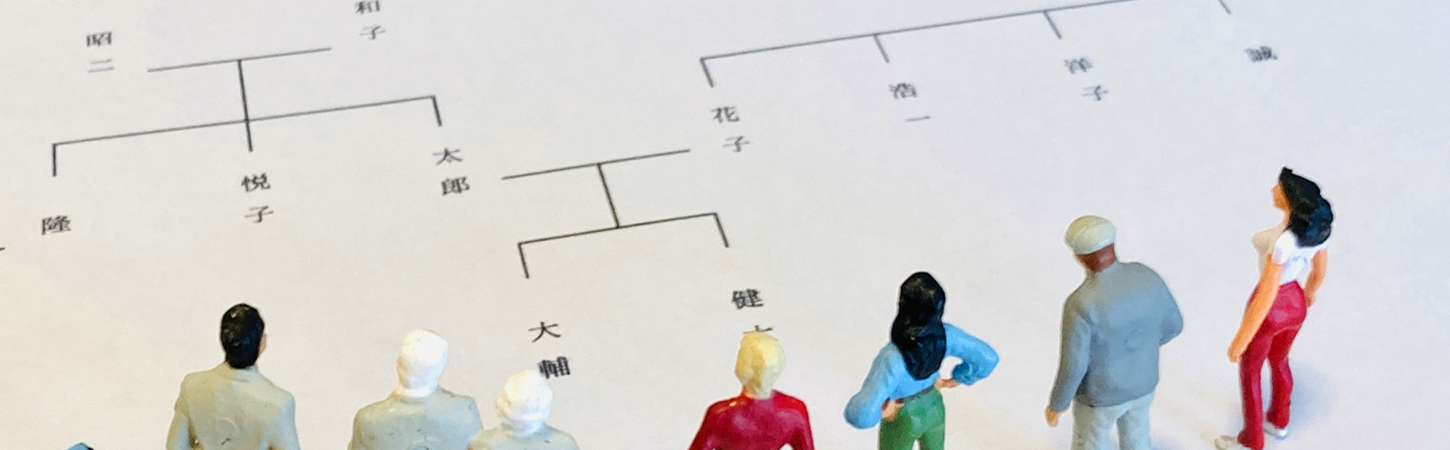親が亡くなったあと、「借金があるかもしれない」「トラブルを避けたい」という理由で相続放棄を考える人は少なくありません。
相続放棄はとても有効な手続きですが、「放棄=すべてゼロになる」わけではないことをご存じでしょうか。
実は、相続放棄をしても守らなければならないルールや、消えない負担がいくつかあります。
知らずにいると、後から思わぬ請求やトラブルにつながることも。
この記事では、相続放棄を検討する方が知っておくべき「3つの注意点」を、専門知識がない方でも理解できるようにやさしく解説します。
1・相続放棄には“期限”がある(3か月ルール)
相続放棄には、亡くなったことを知ってから3か月以内という期限があります。
これを「熟慮期間」と呼びます。
この期間を過ぎてしまうと、
-
自動的に通常の相続人と同じ扱い
-
借金も財産もすべて相続する
ということになってしまいます。
もし「借金があるかもしれない」「財産の内容がよくわからない」という場合は、家庭裁判所に“熟慮期間の延長”を申請することも可能です。
迷っている人は、早めの確認がとても大事です。
2・放棄しても“相続財産の管理義務”が残ることがある
意外と知られていませんが、相続放棄をする前は、相続人に財産を適切に管理する義務があります。
たとえば、
-
空き家が放置されて倒壊しそう
-
ペットが残されている
-
未払いの公共料金がある
-
荷物が大量に残っている
など、近隣トラブルにつながる行為を放置すると、後から別の責任問題に発展することがあります。
相続放棄を予定していても、申述(手続き)が家庭裁判所で受理されるまでは管理義務が残る点に注意が必要です。
3・相続放棄しても“支払いが必要なケース”がある
相続放棄は万能ではありません。
特に、次のようなケースは放棄しても負担が残る可能性があります。
(1)連帯保証人になっていた場合
親が借金の連帯保証人になっていた場合、その責任は相続放棄では消えません。
「保証債務」は相続とは別扱いになることがあるためです。
(2)生前の未払い費用
病院代、施設利用料、賃貸の原状回復費など、亡くなる直前の支払いは“相続とは別の請求”として届くことがあります。
(3)遺品整理や住宅の片付け費用
放棄しても遺品整理や退去手続きは必要になるケースがあります。
賃貸の場合は大家さんとのやり取りでトラブルが生じることも。
“相続放棄=すべて何もしなくていい”ではない点はしっかり押さえておきたいところです。
まとめ:放棄は有効だが、事前の理解と準備がとても大切
相続放棄は、借金のリスクを避けるための強い手続きですが、
-
期限があること
-
管理義務が残ること
-
放棄しても消えない負担があること
など、気をつけるポイントがいくつもあります。
迷ったら一人で抱え込まず、専門家へ早めに相談することで、余計なトラブルを避けることができます。
相続は状況によって必要な対策が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるの?」という疑問があれば、気軽に相談してみてください。
あなたの状況に合った最適な方法を一緒に考えていきましょう。